エビやカニ自体は赤くない?
エビやカニと言ったら赤いイメージがありますよね?でも、生きているエビやカニって鮮やかな赤色ではなく、茹でると赤くなります。彼らの赤色はアスタキサンチンという赤い色素を持っているからです。でも茹でる前と茹でる後とで色が変化するのはなぜなんでしょうか?これは、赤い色素であるアスタキサンチン自体は赤いのですが、このアスタキサンチンがエビやカニがもっているタンパク質とくっつくと黒っぽい色に変化します。なので、生きたエビやカニは鮮やかな赤色ではないです。茹でると鮮やかな赤色に変化するのは、タンパク質とくっついたアスタキサンチンが熱を加えることによって、タンパク質から離れて元の赤色が復活するからです。タンパク質は熱に弱いため、熱湯で茹でられると、壊れてしまい、アスタキサンチンを放出します。
アスタキサンチンってどんな成分?

アスタキサンチンは人参に含まれるβカロテンやトマトに含まれるリコペンと同類のカロテノイドと呼ばれる分類の物質です。カロテノイドは、青色で書いた二重結合がひとつおきにずらーっと並んだ形をしているのが特徴です。この形を化学的には共役二重結合と呼びますが、この長さが変わると色が変化します(吸収する光が変化します)。リコペンは青や緑の光を吸収するため、反射する光は赤色だけになります。そのため、リコペンを含むトマトは赤く見えます。同じ形を持っているアスタキサンチンは赤色をしています。ちなみに六角形のベンゼンは繰り返し二重結合を3つしか持っていないので、目に見える光を吸収出来ません。吸収する光は短い波長の光(紫外線)のため、液体のベンゼンは透明に見えます。
 “EM spectrumrevised” © Philip Roman, Gringer (Licensed under CC BY 3.0)
“EM spectrumrevised” © Philip Roman, Gringer (Licensed under CC BY 3.0)アスタキサンチンは微生物が作る
このアスタキサンチンはエビやカニが自分で作っているわけではないようです。実は、餌にアスタキサンチンが含まれていてそれを食べるから体にアスタキサンチンが溜まって、赤色になっているみたいです。このアスタキサンチンを作っている微生物はヘマトコッカスという種類の藻類で、紫外線から身を守るためにアスタキサンチンという色素を作っています。そのため紫外線から身を護る作用があるようです。光を浴びやすい皮膚や目を保護する作用を調べた研究があります。皮膚の老化などを防ぐ効果があるかもしれませんね。
アスタキサンチンをたくさん取ると人間も体が赤くなったりするのでしょうかね?
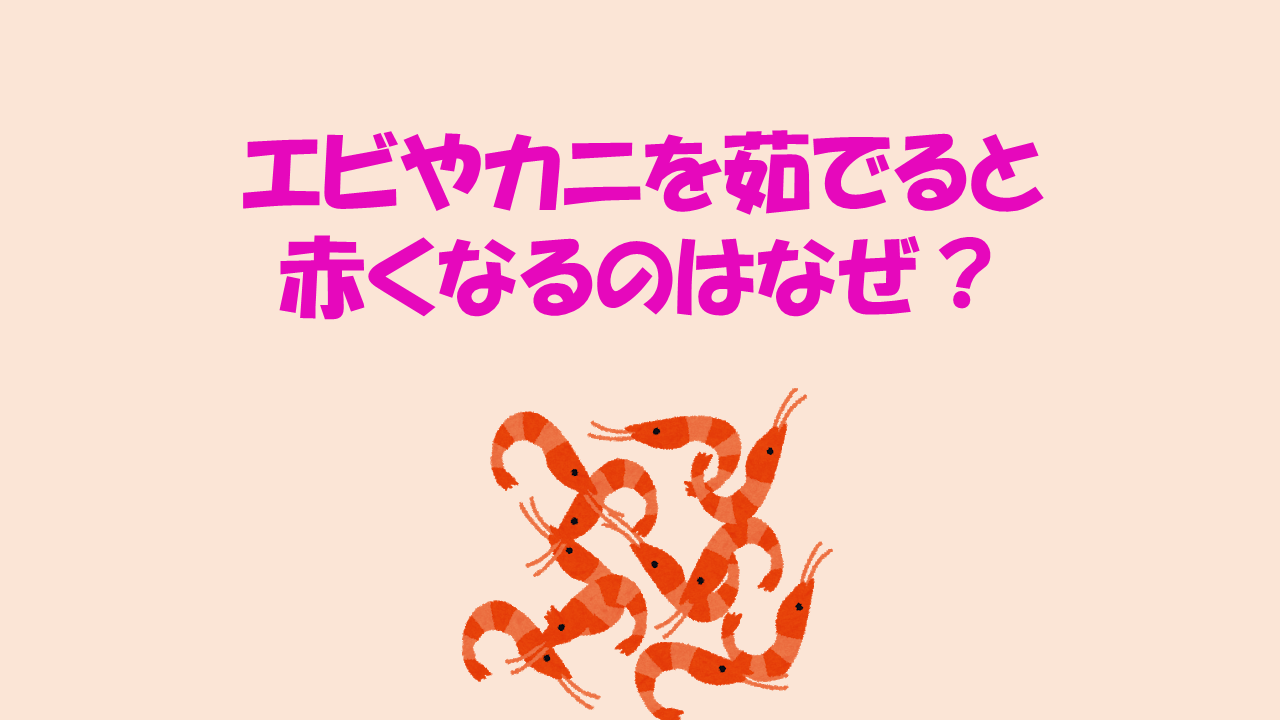
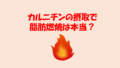

コメント